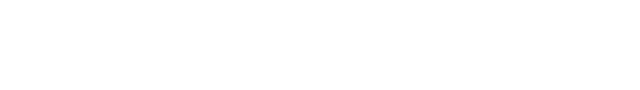発熱外来
当院では発熱外来を設けております。感染対策のため、発熱者用の診察室と待合を別に設けており、院内感染予防に努めております。また、お車でお越しの場合はクリニック前面に8台の駐車スペースがあり、駐車場内での待機も可能です。このページでは発熱の原因となる疾患や受診のタイミング、発熱時の生活上の注意について解説しております。
発熱とは?
発熱には様々な定義があります。一般的には体温(腋窩温)が37.5℃以上の場合を医学的に発熱と呼びます。発熱の多くは感染症や体内の炎症が原因で起こっています。感染症で体温が上がるのは、体内に侵入した病原体を免疫反応によって退治しようとしている時の反応で熱が生じるためです。発熱自体は生理現象であり、極端な高熱でなければ心配はないとされています。
発熱時の対応は?
発熱は体内のエネルギーを消費して起こる生理現象です。そのため、発熱した際は、無駄なエネルギーを使わないように安静にして、体力を温存することが重要です。高熱でなければ、長湯さえしなければ、入浴も可能です。発熱時は水分を失いやすいので、脱水症状にならないように水分摂取を心掛けましょう。
発熱が問題となるのは、発熱による倦怠感で食事がとれなかったり、眠れなかったりすることです。このようなことがあれば解熱剤の内服をお勧めします。発熱が持続する場合は、発熱の原因となる疾患の検索・治療も必要になりますので受診をお勧めします。
急に高熱が出た時の対応は?
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの流行期は、突然、高熱が出たと言われる患者様が多くおられます。大切なのは、慌てずに適切な受診行動を行うことです。
インフルエンザや新型コロナウイルスなどのウイルス感染症は基本的には自然治癒することが多く、基礎疾患などがない場合は過剰に心配する必要はありません。
特に、発熱の原因を診断して学校や職場に連絡するために受診を希望される場合は、発熱してから18-24時間以上経過してからの受診をお勧めします。というのも、検査キットなどの抗原検査は発熱早期(12時間以内)であった場合は、抗原が十分に増えておらず、検査をしても正しく診断できない可能性があります。もちろん、高熱で食事がとれない、自宅に解熱剤がなく倦怠感が強い場合は翌朝の受診をお勧めします。
平熱が低い方の発熱について
患者様の中には「いつも体温が35℃なのに、今は36.5℃だから発熱ではないか?」
と不安になり受診される方もおられます。体温には個人差があります。ある研究では、数千人の日本人の平均体温を調べたところ、36.5-37.2℃とであったという報告があります。このことから「平熱が低い」という状態は、実際には測定方法が不適切である可能性、周囲の気温の影響、体温の日内変動による影響などが考えられるのです。また、発熱の始まりを捉えている可能性もあります。医学的には37.5℃以上が発熱ですので、随伴する症状(咳、咽頭痛、倦怠感)などがない場合は受診の必要性は低いと考えられます。
体温の日内変動について
体温には日内変動があります。時間帯だけでなく、運動、食事、睡眠などによっても体温は変動します。具体的には早朝が最も低く、夕方に最も高くなります。その後は夜にかけて体温が下がっていきます。食事摂取や、運動後も体温の上昇が起こります。日内変動は1℃程度あると言われています。
発熱が出た際に考えられる疾患
発熱は体内の感染や炎症が原因で起こっており、体内での何らかの異常を示すサインでもあります。治療においては発熱それ自体よりも、発熱の原因となっている疾患を見つけ出すことが重要です。実際には下記の様に、発熱をきたす疾患は多岐にわたり、発熱以外の症状が何であるか、どういう時に症状が起きたかが重要です。参考までに、以下に発熱の原因となる疾患で代表的な疾患を列挙します。
①インフルエンザや新型コロナウイルスなどによるウイルス感染症
最も頻度が高いと考えられるのが、ウイルスによる感染症です。発熱に加えて、咽頭痛や咳、痰などの症状を伴うことがあります。ウイルス感染に対しては抗生物質が無効です。インフルエンザや帯状疱疹ウイルスなど特殊なもの以外は、症状を軽減する対症療法を行い、自身の免疫力での治癒を助けます。
②咽頭炎
咽頭とは喉の奥の部分のことで、ウイルスによる咽頭炎、細菌による咽頭炎があります。痰や咳が出たり、飲み込むときの痛み(嚥下痛)で食事摂取が困難になったりする方もおられます。首のリンパ節が腫脹することで痛みや違和感も見られます。細菌感染が疑われる場合は抗生剤による治療を行います。
③副鼻腔炎
蓄膿症とも呼ばれます。ウイルス感染や細菌感染、アレルギーなどをきっかけにして鼻の粘膜が腫れ、副鼻腔と鼻腔の交通が閉塞してしまい、鼻水などが適切に排出されなくなります。副鼻腔に鼻水・膿がたまり発熱、頭痛、痰を認めます。
④肺炎
肺にウイルスまたは細菌が感染して炎症が生じる疾患です。肺炎は日本人の死因の第5位となっており、命に関わる病気の一つです。症状としては、息切れがする、咳が出るなどの症状他に、倦怠感からくる食事摂取量の減少もあります。また、高齢者では増悪しやすいことも知られております。そのため、高齢者では肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチンの接種が重症化リスクの軽減のために必要です。重症度分類に応じて、外来治療、入院治療を判断します。
⑤胆嚢炎
胆嚢は肝臓で作られた胆汁を一時的に貯蔵しておく袋状の器官です。胆嚢に感染が起こることを胆嚢炎と呼びます。その原因の多くが、胆嚢内にできた石が胆嚢の入り口、または胆管内に嵌まり込み、胆汁の流れをうっ滞させることで起こります。症状は発熱、右上腹部痛、黄疸などがあります。治療法としては絶食、抗生剤投与に加えて、内視鏡的治療が必要になることも多く、入院加療になるケースが多いです。
⑥腎盂腎炎
腎盂腎炎は腎臓の腎盂(尿が作られて出てくるところ)周囲の組織が細菌により感染を引き起こすことで生じる上部尿路感染症です。膀胱炎などの下部尿路感染症から尿管を逆行性に細菌が上行することで腎臓に達し、感染を引き起こします。原因となる菌は大腸菌が多いとされます。症状は発熱、腰背部痛などが典型的です。腎盂腎炎は発熱が高熱になりやすく、敗血症にもなりやすい疾患の一つでもあるので、早期の診断・治療が重要です。診断には尿検査、血液検査、エコー検査が重要です。
⑦膀胱炎
膀胱炎は膀胱粘膜に炎症が起こる疾患です。尿道が短いため女性に多い疾患です。症状は頻尿や排尿時痛があります。発熱もそれほど高くないことが多いです。水分摂取と抗生剤の内服が有効です。
⑧感染性腸炎
細菌やウイルスなどの病原体が原因で起こる腸炎の総称です。ノロウイルスやロタウイルスが有名です。潜伏期間は1-3日程度で、症状は嘔吐・下痢、発熱、腹痛です。特別な治療法はなく、整腸剤や水分補給などの対症療法で自然治癒を待つことが多く、有症期間は5日程度と言われています。高齢者や乳幼児では脱水症に注意が必要であり、家庭内での感染にも注意が必要です。
⑨急性虫垂炎(盲腸炎)
盲腸という部分にある虫垂に炎症が起こる病気で、一般的には盲腸炎と呼ばれることもあります。腹痛と37~38℃の発熱が生じ、吐き気や嘔吐を伴います。腹痛は最初、みぞおちから生じ、徐々に右下腹部に移動することがあります。