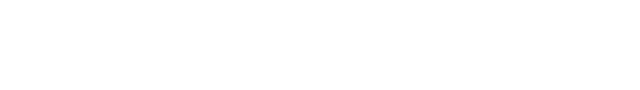痛風/高尿酸血症
「朝起きたら足の親指が真っ赤に腫れて、歩けないほど痛い」──このような症状で突然始まるのが「痛風発作」です。痛風は、血液中の尿酸が高くなり、その結晶が関節に沈着して炎症を起こす病気です。ここでは、高尿酸血症と痛風についてガイドラインなどを参考に一般的な内容を解説していきます。
高尿酸血症とは
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が7.0mg/dLを超えた状態を指します。近年、食生活の欧米化や生活習慣の変化により、患者数は増加傾向にあり、日本では約1000万人以上が高尿酸血症と推定されています。痛風の患者数も増加しており、2016年時点で約110万人に達しています。
尿酸は、体内でプリン体が分解されてできる老廃物で、通常は腎臓から尿として排泄されます。しかし、以下のような要因で尿酸が過剰に産生されたり、排泄がうまくいかなくなると、血中に尿酸が蓄積し、高尿酸血症となります。
- プリン体の過剰摂取(レバー、干物、魚卵、アルコールなど)
- 肥満やメタボリックシンドローム
- 腎機能の低下
- 遺伝的要因(ABCG2遺伝子の機能低下)
- 利尿薬や抗がん剤の使用
尿酸値が高い状態が続くと、関節や腎臓に尿酸結晶が沈着し、痛風発作や腎障害、尿路結石などを引き起こすリスクが高まります。
痛風発作の引き金とは?
痛風は感染症ではないため、起炎菌による発症ではありません。ここでいう「起炎因子」とは、痛風発作を引き起こすきっかけとなる要因を指します。痛風発作は、関節内に沈着した尿酸結晶に対して免疫細胞が反応し、炎症を起こすことで発症します。
痛風発作の誘因として頻度が高いものは以下の通りです:
- 急激な尿酸値の変動(尿酸降下薬の開始直後など)
- 過度の飲酒や暴飲暴食
- 脱水状態(発熱、下痢、運動後など)
- 手術や外傷後のストレス
- 急激な体重減少や断食
これらの因子が関節内の尿酸結晶を刺激し、炎症反応を引き起こすことで、痛風発作が起こります。特に足の親指の付け根(第一中足趾関節)に好発し、突然の激痛と腫れを伴います。
痛風の症状について
高尿酸血症自体には自覚症状がありませんが、尿酸値が高い状態が続くと、以下のような症状が現れることがあります。
痛風発作(急性痛風関節炎)
- 突然の激しい関節痛(特に足の親指、夜間~早朝に多い)
- 関節の腫れ・発赤・熱感
- 発熱や倦怠感を伴うこともある
- 発作は1週間程度で自然軽快するが、再発を繰り返すことがあります。
初回は足の親指に発症することが多いですが、くり返すと足首、膝、手首など他の関節にも広がることがあります。
慢性期の症状
- 痛風結節:関節周囲に尿酸結晶が沈着し、こぶ状に腫れる
- 腎障害:尿酸結晶が腎臓に沈着し、慢性腎臓病の原因となる
- 尿路結石:尿酸が結晶化して尿路に石ができる
痛風発作は、尿酸値が最も高い時ではなく、急激に変動した時に起こりやすいという特徴があります。
痛風の治療法について
当院では、急性期の対処と長期的な再発予防の両面から治療を行います。
急性痛風発作の治療
- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):第一選択薬。痛みと炎症を抑える
- グルココルチコイド(ステロイド):NSAIDsが使えない場合に使用
- コルヒチン:発作初期に有効。予防投与にも使われる
※発作中は尿酸降下薬の開始・変更は避けるのが原則です。
高尿酸血症の治療
- 生活習慣の改善
- プリン体の摂取制限(レバー、干物、魚卵、アルコールなど)
- 水分摂取
- 減量と適度な運動
- 薬物療法
- 尿酸生成抑制薬(アロプリノール、フェブキソスタットなど)
- 尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン、プロベネシドなど)
- 尿アルカリ化薬:尿路結石予防に併用されることも
治療目標は、血清尿酸値を6.0mg/dL以下に維持することです。痛風結節のある場合は、より厳格な管理が求められます。
痛風についてのよくある質問
Q1. 痛風発作がないのに尿酸値が高いままでも治療は必要ですか?
A1. はい。無症状の高尿酸血症でも、動脈硬化や腎障害のリスクが高まりますので、体質や合併症の有無を考慮して治療を検討します。
Q2. 尿酸値はどれくらいが目標ですか?
A2. 発作予防には6.0mg/dL未満が推奨されます。すでに腎障害がある場合はより厳密に管理します。
Q3. 一度発作が治れば薬はやめてもいいですか?
A3. 再発予防のためには、継続的な治療が重要です。急に薬をやめると、再発する可能性が高まります。
最後に
痛風は「贅沢病」とも呼ばれていましたが、今では生活習慣病のひとつとして、働き盛りの方や高齢者にも増えています。特に尿酸値が高いまま放置すると、腎臓や血管にも悪影響が出てきます。動脈硬化とも関連があり、循環器領域の患者さんにも多く高尿酸血症の治療を行っている方がおられます。当院では、循環器や腎臓の状態も踏まえながら、痛風の根本治療に取り組んでいます。急な発作時の対応はもちろん、再発予防を含めた継続的なフォローもお任せください。あなたの“関節”と“血管”を一緒に守っていきましょう。