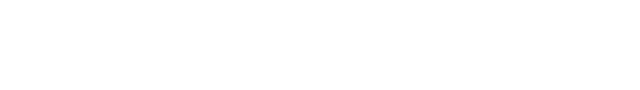閉塞性動脈硬化症
「歩くとふくらはぎが痛くなり、少し休むとまた歩ける」
「足が冷たい、しびれる、色が悪い」──
このような症状がある方は、**閉塞性動脈硬化症(ASO)**の可能性があります。
閉塞性動脈硬化症とは、足の動脈に動脈硬化が起き、血管が狭くなったり詰まったりすることで、十分な血流が届かなくなる病気です。
特に糖尿病、高血圧、高脂血症、喫煙歴などの生活習慣病をお持ちの方に多く見られます。
私たち**ゆうひ内科循環器クリニック(横川駅徒歩8分)**では、血管年齢測定(ABI/PWV)やエコー検査を用いて、足の血流状態を丁寧に評価し、早期治療を目指しています。
閉塞性動脈硬化症の原因について
閉塞性動脈硬化症は、足の動脈に動脈硬化(血管が硬く狭くなる変化)が起こることが直接の原因です。
【動脈硬化を引き起こす主な要因】
-
糖尿病
-
高血圧
-
高脂血症(コレステロール値の異常)
-
喫煙(ニコチンの血管収縮作用)
-
加齢(特に60歳以上)
-
慢性腎臓病・透析治療中
これらの因子が複合的に重なって動脈の内側にコレステロールなどが沈着し、血液の通り道が狭くなる・詰まることで発症します。
心臓病(狭心症・心筋梗塞)や脳卒中と同じく、動脈硬化性疾患の一種であり、全身の血管病としてとらえることが重要です。
閉塞性動脈硬化症の症状について
初期は無症状のことも多いですが、進行すると次のような症状が現れます。
【主な症状】
-
間欠性跛行(かんけつせいはこう)
→ 歩いていると足がだるくなったり痛くなり、休むと再び歩けるようになる状態 -
足の冷感やしびれ
-
足先の色が悪い、蒼白や紫色に見える
-
足の脈(足背動脈)が触れにくい
-
重症になると安静時にも痛み(安静時疼痛)や潰瘍、壊死
歩行に支障が出たり、最悪の場合は足の切断に至ることもありますので、早めの診断・対応が極めて重要です。
閉塞性動脈硬化症の病期分類
代表的な分類として「フォンテイン分類」があります。
| 病期 | 症状 |
|---|---|
| I度 | 無症状(血流低下はあるが自覚症状なし) |
| II度 | 歩行時にふくらはぎの痛み(間欠性跛行) |
| III度 | 安静にしていても足の痛み(安静時疼痛) |
| IV度 | 潰瘍や壊死(皮膚が黒くなる) |
II度の間に診断と治療を始めることが、重症化を防ぐ鍵です。
閉塞性動脈硬化症の治療法
治療の基本は動脈硬化の進行を抑え、血流を改善することです。
1. 検査
当院では以下のような検査を行っています。
-
ABI(足関節上腕血圧比)
→ 足の血管の詰まり具合を測定 -
PWV(脈波伝播速度)
→ 血管の硬さ(血管年齢)を評価 -
下肢動脈エコー検査
→ 血管の狭窄や血流の様子を視覚的に確認 -
必要に応じてCTや血管造影を紹介先で実施
2. 薬物療法
-
抗血小板薬(血液をサラサラに)
-
コレステロールを下げる薬(スタチン系など)
-
血管拡張薬
-
糖尿病や高血圧のコントロール
3. 運動療法
-
歩行トレーニング(有酸素運動)
→ 血流を改善する効果が科学的に実証されています。 -
ただし、痛みが出すぎない範囲で行う必要がありますので、医師の指導のもと進めていきましょう。
4. 手術・血管内治療(当院から専門施設へ紹介)
-
バルーンによる血管拡張やステント留置
-
外科的なバイパス手術
これらは重度の狭窄や壊死がある場合に必要となることがあります。
閉塞性動脈硬化症についてのよくある質問
Q1. 片足だけがだるくなるのはASOですか?
A1. 可能性はあります。片側の足だけに痛みやしびれが出るのは典型的な特徴です。一度、ABI検査をおすすめします。
Q2. この病気は治りますか?
A2. 血管の狭窄は元に戻すのが難しいですが、早めの治療と生活習慣の見直しで進行を防ぐことが可能です。
Q3. 糖尿病がありますが、関係ありますか?
A3. 関係大いにあります。糖尿病はASOの主要なリスク因子の一つであり、血管が脆くなりやすくなります。
Q4. 歩くだけで治療になるのですか?
A4. はい、正しい方法での歩行トレーニングは治療効果があることがわかっています。ただし、個々に合った指導が必要です。
院長より
閉塞性動脈硬化症は、見逃されやすいけれども、生活に大きく影響を与える血管の病気です。
特に「歩くと足がだるくなる」「足が冷たい」といった症状がある方は、放っておかず早めにご相談ください。
私たちゆうひ内科循環器クリニックでは、血管年齢の測定や下肢エコーなどの検査設備を整え、専門的な視点で診断と治療を行っています。
中高年の方、生活習慣病をお持ちの方の“足からの健康チェック”としても、ぜひ一度受診をご検討ください。