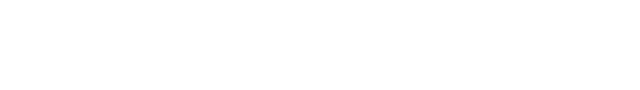蜂窩織炎
蜂窩織炎は、皮膚の小さな傷やささくれ、虫刺されなどを通じて、皮膚の奥に細菌が侵入することで発症します。
【主な原因菌】
-
溶血性連鎖球菌(溶連菌)
-
黄色ブドウ球菌
【リスク因子(なりやすい背景)】
-
足のむくみ(リンパ浮腫・静脈瘤)
-
糖尿病や免疫力の低下
-
高齢・寝たきりの状態
-
足の皮膚の乾燥・水虫(白癬)
-
外傷・虫刺され・手術後の傷口
蜂窩織炎の予防には、「皮膚を清潔に保つこと」と「むくみや乾燥を改善すること」がとても重要です。
蜂窩織炎の症状について
蜂窩織炎の主な症状は以下の通りです。
-
皮膚の赤み(発赤)
-
腫れ(腫脹)
-
熱をもった痛み(発熱・圧痛)
-
皮膚の表面がつっぱる、光沢が出る
-
倦怠感、寒気、38度以上の発熱
症状は片側の足に集中することが多く、進行すると腫れが拡大し、歩くのもつらくなることがあります。また、高熱が出ると入院が必要となるケースもありますので、早期診断・早期治療が大切です。
蜂窩織炎の病型と重症度
蜂窩織炎は、軽症から重症まで症状に差があり、重症化すると敗血症や壊死性筋膜炎などの重大な合併症に至ることもあります。
| 病型・重症度 | 特徴 |
|---|---|
| 軽症 | 赤みと軽い腫れ、局所の熱感、微熱程度。内服で治療可能。 |
| 中等症 | 腫れが広がる・痛みが強い・発熱・倦怠感。点滴治療が必要になることも。 |
| 重症 | 高熱・強い痛み・皮膚の壊死・膿瘍形成。入院が必要。 |
当院では、血液検査や超音波などを活用し、重症度を見極めた上で外来での抗菌薬治療や紹介先の判断を迅速に行います。
蜂窩織炎の治療法について
蜂窩織炎は、原因菌に対する抗菌薬(抗生物質)による治療が基本です。
当院で行っている治療
-
抗菌薬の内服(セフェム系・ペニシリン系など)
-
解熱鎮痛剤の処方
-
患部の安静・挙上指導
-
皮膚の保護・水虫などの併存病変の治療
-
むくみ対策の指導(弾性ストッキングなど)
-
点滴治療(必要に応じて)
皮膚の炎症は見た目で軽そうに見えても中で進行していることがあるため、自己判断は禁物です。
また、一度治っても繰り返しやすいため、再発予防の観点からも継続的なフォローアップが重要です。
蜂窩織炎についてのよくある質問
Q1. 足の赤みと熱っぽさがありますが、すぐに受診したほうがいいですか?
A1. はい、**早期に受診いただくことで内服薬のみで治まることもあります。**放置すると悪化することがあるため、お早めにご相談ください。
Q2. 水虫がありますが、蜂窩織炎に関係ありますか?
A2. あります。**水虫によって皮膚のバリアが弱くなっており、細菌が侵入しやすくなります。**当院では水虫の治療もあわせて行っています。
Q3. 発熱もあり心配です。自宅でできることはありますか?
A3. 赤く腫れている部分は冷やさずに、安静にして心臓より高い位置に上げると腫れが引きやすくなります。ただし、発熱がある場合は早めの医療機関受診が重要です。
Q4. 繰り返さないためにはどうすればいいですか?
A4. 皮膚の保湿・清潔の保持・むくみの管理・水虫の治療などが有効です。定期的なケアが予防につながります。
院長より
蜂窩織炎は、見た目よりも深い部分で炎症が広がっていることがあり、思った以上に長引いたり、再発することのある病気です。
当院では、糖尿病や高血圧、動脈硬化などの背景疾患も含めて全身の健康状態を確認しながら、適切な抗菌薬や再発予防の指導を行っています。
「なんだか腫れてきた」「熱を持ってるかも?」という段階で、気軽にご相談いただければと思います。