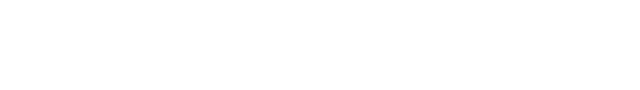虫垂炎
急性虫垂炎とは?
急性虫垂炎とは、小腸側の大腸である盲腸にある虫垂という小さな袋状の臓器が炎症を起こす病気です。虫垂は大腸の一部であり、免疫機能に関与していると考えられていますが、その役割は未だ完全には解明されていません。急性虫垂炎は、一般的に20歳代から40歳代に多く発症しますが、全年齢層で見られる疾患です。
急性虫垂炎の原因は、虫垂内に閉塞が生じることによると考えられており、糞石(便の石)やリンパ組織の肥大、あるいは体外からの微生物感染などが起こすとされています。閉塞により虫垂内に細菌が繁殖し、炎症が進展すると、虫垂の壁が壊死する場合もあり、穿孔や腹膜炎といった合併症が生じるリスクがあります。疫学的には、日本国内では年間約10万人前後が急性虫垂炎で救急受診を必要としているとされます。
症状の発症や経過
急性虫垂炎は、初期には比較的軽度の腹痛やみぞおちの違和感から始まることが多いです。症状が進行するにつれて特徴的な症状が現れます。
・初期症状
みぞおちのあたりの痛みを生じることがあり、胃が痛いという症状で来院される方も比較的多くみられます。特徴的な症状としては右下腹部の鈍い痛みがあり、食欲不振や吐き気、微熱が伴います。また、発症直後は全般的な倦怠感が見られることもあります。
・症状の進行
痛みが右下腹部に局在化して、次第に鋭く激しい痛みに変わります。歩行や咳などの際に痛みが増強することがあり、体位の変換が困難になる方もおられます。さらに、発熱が進行して38℃以上に上昇することもあり、全身のだるさや悪寒を感じる場合も見られます。
・経過と合併症のリスク
急性虫垂炎は、早期に治療が開始されると、抗生剤投与などの薬物療法でも治療ができることが多いです。しかし、治療が遅れ、重症化すると虫垂が穿孔し、腹膜炎や膿瘍形成といった重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。典型的な症状には、腹部全体への激しい痛み、発熱、、嘔吐、便秘などが挙げられ、症状の現れ方や持続期間は個人差があります。
急性虫垂炎の病態
急性虫垂炎の病態は、虫垂内の閉塞とそれに伴う細菌感染によって進行します。
・虫垂内閉塞
虫垂内において、便石やリンパ組織の肥大などが原因で閉塞が生じると、正常な分泌物や細菌が排出できなくなります。これにより、虫垂内圧が上昇し、血流障害がおこり、細胞が酸素不足に陥ります。
・細菌の増殖と炎症
閉塞状態により、虫垂内に常在する細菌が急激に増殖します。細菌の増殖に伴い、体は免疫反応を開始し、炎症細胞(好中球、リンパ球など)が集まり、炎症反応を引き起こします。これにより、虫垂壁が腫れ、最終的には炎症が進んで虫垂壁が壊死することがあります。
・穿孔と腹膜炎
炎症が進行して虫垂壁が壊死すると、虫垂が穿孔し、感染性の内容物が腹腔内に漏れ出すことがあります。これが引き金となり、腹膜炎へと進展するケースもあります。
虫垂炎の治療法
急性虫垂炎の治療は、できるだけ早期に虫垂の炎症や感染を根絶することが目的です。治療法には、以下の2つの大きなアプローチがあります。
1. 薬物療法と輸液治療
・初期治療(抗菌薬の投与)
急性虫垂炎の初期段階では、抗菌薬を用いて細菌の増殖を抑え、炎症の拡大を防ぐことが試みられる場合もあります。特に、診断が早期に行われ、炎症が軽度な場合は、入院して点滴による抗菌薬投与や輸液治療が行われることがあります。また、脱水状態に陥らないよう、適切な水分・電解質補給や栄養管理が重要です。
・痛みや発熱の管理
解熱鎮痛剤や制酸剤が、痛みの緩和や胃腸の負担軽減の目的で用いられることもあります。しかし、基本的には抗菌薬治療と支持療法が中心となります。
2. 手術療法(虫垂切除術)
・基本的な治療法
急性虫垂炎の多くの場合、特に症状が進行して穿孔や膿瘍形成のリスクが高い場合、虫垂切除術が標準的な治療となります。手術は、開腹手術または腹腔鏡下手術のいずれかにより行われ、虫垂の除去により炎症の進行を防ぎ、合併症を回避します。
・手術のタイミング
急性虫垂炎の手術については、血液検査や画像診断所見を総合して外科医が判断します。抗生剤での治療が難しい、穿孔のリスクが高い、もしくは穿孔しているという場合は手術治療になります。
・術後管理
手術後は、感染予防や脱水管理、痛みの管理などが徹底され、再発予防と完全回復を目指します。術後の経過観察として、血液検査が定期的に行われることも一般的です。
急性虫垂炎では、上記の様な治療が行われます。当院では、適切な治療を心がけております。また、入院や手術が必要な際は迅速な対応可能施設への紹介を行っております。右下腹部痛や発熱といった症状がみられる方、症状について疑問がある際はお気軽に当院へご相談ください。