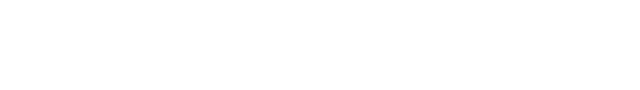甲状腺機能異常
甲状腺機能障害について
甲状腺は前頸部にある臓器で、全身の代謝・体温調節に重要な役割を果たすホルモン(T3、T4)を産生する内分泌腺です。これらのホルモンの分泌量が適正な範囲を逸脱すると、体内の代謝バランスが乱れ、甲状腺機能亢進症(ホルモン過剰状態)または甲状腺機能低下症(ホルモン不足状態)という疾患が発症します。
甲状腺機能障害の疫学的な特徴について
甲状腺機能亢進症
・特に若年女性に多く、男女比は約7:1と女性に顕著な傾向があります。
・ストレスや環境因子、遺伝的素因も重なり、家族歴のある方はリスクが高くなるとされています。
甲状腺機能低下症
・男女比1:4で、20-50歳の女性に多く、加齢とともに増加する疾患です。
・原因に自己免疫性甲状腺炎(橋本病)があり、有病率は日本国内で約2~3%と報告されています。
・特に中高年、閉経後の女性に多く見られ、加齢とともに頻度が上昇する傾向があります。
・遺伝的背景や他の自己免疫疾患との関連も指摘され、初期は自覚症状が乏しい場合もあるため、定期検診での早期発見が重要です。
甲状腺機能障害の症状
甲状腺機能亢進症により起こる症状
・代謝亢進による症状:体重減少、過剰な発汗、ほてり、頻脈や動悸、震えなどがみられます。
・神経・精神面の変化:不安感、イライラ、睡眠障害が出現することがあります。
・眼症状:甲状腺眼症として、眼球突出や眼瞼の腫れがみられることもあります。
甲状腺機能低下症により起こる症状
・多くの方には現れませんが、前頸部の違和感を訴える方もおられます。
・代謝低下による症状:体重増加、倦怠感、寒がり、便秘、皮膚や髪の乾燥がみられます。
・循環器・神経系への影響:心拍数の低下、むくみ、筋力低下、集中力の低下や記憶力障害、うつ状態を伴うこともあります。
・女性特有の症状:月経不順や不妊、閉経後の様々な不調が現れることがあります。
病態について
甲状腺機能亢進症の病態
・自己免疫性反応により産生される甲状腺刺激ホルモン受容体抗体(TRAb)が、TSH受容体に結合して過剰な甲状腺ホルモン(T3、T4)の生成・分泌を促進する点にあります。
・結果として、交感神経系が刺激され、血管拡張、心拍数増加、体温上昇などの全身的な代謝亢進が引き起こされます。
・また、眼窩内での免疫反応や炎症が、眼球突出といった特有の所見を生じさせます。
甲状腺機能低下症の病態
・自己免疫性甲状腺炎(橋本病)により、甲状腺組織が破壊され、甲状腺ホルモンの合成・分泌能力が低下することです。
・ホルモン不足により、全身の代謝が低下し、心拍数やエネルギー産生、たんぱく質合成が著しく低下します。
・細胞レベルでは、基礎代謝の低下に伴い、各臓器の働きが鈍くなり、体温低下やコレステロール値の上昇といった二次的な変化も見られます。
両疾患は、いずれも自己免疫性疾患としての側面を持ちますが、甲状腺ホルモンの過剰と不足という逆の現象により、体全体に及ぼす影響は大きく対照的です。
甲状腺機能障害の検査について
問診と身体診察
まずは、医師による問診と身体診察が行われます。問診では、全身の不調の他、体重変動、動悸・震え、発汗、寒がり、便秘、疲労感、月経の乱れなど、各疾患に特徴的な症状が確認されます。また、家族歴や既往歴、生活習慣(たとえば喫煙やストレス)についてもお伺いします。身体診察では、甲状腺の大きさや質感、眼の突出(特に亢進症の場合)など、触診や視診によって異常の有無を確認します。
血液検査による甲状腺機能の評価
次に、血液検査を行い、甲状腺ホルモンの濃度を測定します。主な検査項目は以下のとおりです。
-
TSH (甲状腺刺激ホルモン):
・亢進症の場合:TSHは低下しているのが特徴です。
・低下症の場合:TSHは上昇していることが一般的です。 -
FT3およびFT4 (遊離T3, 遊離T4):
・亢進症の場合:FT3、FT4は高値を示し、過剰なホルモン分泌を反映します。
・低下症の場合:これらの値が低下しており、ホルモン不足が認められます。
これらの検査結果により、体内の甲状腺ホルモンの状態を客観的に評価し、どちらの病態であるかの初期的な判断が可能になります。
自己免疫マーカーと抗体検査
甲状腺異常の原因が自己免疫性疾患である場合、特定の抗体の存在が診断のキーとなります。
-
甲状腺刺激ホルモン受容体抗体(TRAb):
主に甲状腺機能亢進症で陽性となり、病態の原因を明らかにします。 -
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)および抗サイログロブリン抗体(TgAb):
これらは甲状腺機能低下症、特に自己免疫性甲状腺炎(橋本病)で高頻度に認められ、診断の補助として利用されます。
治療法について
甲状腺機能亢進症の治療
・薬物療法:まずは抗甲状腺薬(メチマゾール、プロピルチオウラシル)による内服治療が行われ、過剰なホルモン生成を抑制します。
・β遮断薬:心拍数の上昇、震え、動悸などの症状を緩和するために短期間使用されます。
・放射性ヨウ素療法:薬物療法で十分な効果が得られない場合、放射性ヨウ素を用いて甲状腺組織を破壊する方法が適用されます。
・手術療法:重症例や合併症が疑われる場合、部分切除または全摘手術が選択されることもあります。
・治療の選択は、年齢、症状の重症度、妊娠希望の有無など多くの因子を考慮して総合的に判断され、定期的な血液検査を通じたフォローアップが必要です。
甲状腺機能低下症の治療
・甲状腺ホルモン補充療法:レボチロキシン(L‑T4)製剤を用いて不足したホルモンを補充する治療がを行います。血中TSHやFT4の値を基に、適切な用量へ調整しながら長期的に治療を維持します。
・症状のモニタリング:体重増加、疲労感、皮膚状態などの経過や、上記血液検査の観察を行います。
甲状腺機能亢進症と甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの異常分泌という点で共通していますが、その症状、病態、治療法は正反対の特徴を持っています。前者は過剰なホルモンにより代謝の亢進と眼症状を呈し、若年女性に多いのに対し、後者はホルモン不足によって代謝が低下し、慢性的な倦怠感や寒がりなどの症状が顕著で、主に中高年や閉経後の女性に多くみられます。どちらの場合も、定期検診や血液検査を通じた早期発見と、最新の学会ガイドラインに基づいた治療が極めて重要です。
当クリニックでは、甲状腺疾患による循環器症状の治療、甲状腺疾患の経過観察などを行っております。初発の甲状腺疾患の疑いがある方が受診された際は、適切なタイミングで専門医療機関にご紹介することを念頭に診療をしております。ご不明な点やご相談がございましたら、当クリニックまでお気軽にお問い合わせください。