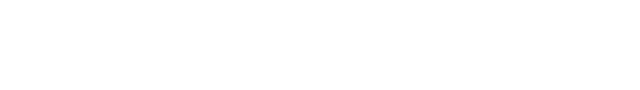感染性胃腸炎
感染性胃腸炎とは?
感染性胃腸炎は、ウイルス、細菌などの病原体が胃や腸の粘膜に感染して炎症を引き起こす疾患です。急性の下痢、嘔吐、腹痛、発熱などの症状が特徴で、特に冬季に流行するウイルス性胃腸炎は集団感染を起こすこともあり、社会的な問題となっています。一方、細菌性胃腸炎は、食中毒などによる集団感染にも関りがあります。
感染性胃腸炎の主要な原因
【ウイルス性胃腸炎】
ウイルス性胃腸炎は、全体の胃腸炎の中でも最も頻度が高く、特に冬季に多く発生します。主要な原因ウイルスとしては以下が挙げられます。
* ノロウイルス
・特徴:非常に強い感染力を有し、わずか10~100個程度のウイルス粒子で感染が成立します。
・感染経路:便や汚染された手指からの糞口感染であり、汚染された食品や水、手指などを介して感染が広がります。
・流行の傾向:高齢者施設、学校、病院などの環境で集団感染が起こりやすい。
・症状:急激な嘔吐、下痢、発熱が見られ、症状は短期間(1~2日)で改善することが多いが、脱水症状に対する注意が必要です。
* ロタウイルス
・特徴:乳幼児に非常に多く見られるウイルスで、重症化すると脱水やけいれんを引き起こすおそれがあります。
・感染経路:主に便や汚染された手指からの糞口感染であり、ウイルスは環境中で長期間生存するため、集団感染が起こりやすい。
・流行の傾向:冬から春にかけて発症することが多いとされます。
・臨床像:激しい水様性下痢、高熱、嘔吐が特徴で、脱水に注意が必要です。
アデノウイルスによる胃腸炎は、季節に関係なく年間を通して発症するのが特徴です。ノロウイルスやロタウイルスのように冬季に流行のピークがあるウイルスとは異なり、アデノウイルスは明確な流行時期がなく、一年中注意が必要とされています
【細菌性胃腸炎】
細菌性胃腸炎は、食品汚染や動物との接触を通じて感染する場合が多く、主な病原体としては以下が挙げられます。
* カンピロバクター
・特徴:鶏肉や生乳を介して感染することが多く、発熱や激しい腹痛、血便を伴うことがあります。
・感染経路:加熱不十分な食品の摂取または汚染による糞口感染。
・疫学:若年成人や小児にも見られ、海外旅行者においても頻度が高い。
・臨床像:下痢、血便、腹痛、発熱などが生じ、哺乳類・鳥類の発症例が報告されています。
* サルモネラ菌、 腸管出血性大腸菌
食品媒介感染の主要原因であり、重症化すると出血性大腸炎や敗血症、さらには腸穿孔などの合併症を引き起こすことがあります。
症状の発症時間と経過
感染性胃腸炎は、病原体に感染してから通常数時間~1日以内に症状が現れる急性疾患です。
【発症時間】
・ウイルス性の場合、ノロウイルスは感染後12~48時間程度で症状が出始めることが多いです。
・ロタウイルスは乳幼児では感染後1~3日で発症し、成人ではやや発症が遅れる傾向があります。
・細菌性の場合は、たとえばカンピロバクターでは感染後2~3日ほどで症状が現れるとされています。
【症状の経過】
・初期には急激な嘔吐や下痢が顕著に現れ、脱水や体力低下を引き起こします。
・ウイルス性胃腸炎では、多くの場合、症状は1~3日でピークに達し、通常は4~5日以内に自然回復することが一般的です。ただし、乳幼児・高齢者では脱水が重篤となり、注意深い管理が必要です。
・細菌性胃腸炎は、症状の重さに個人差があり、場合によっては長引き、重症化しやすい場合があります。血便や高熱、激しい腹痛などがみられる場合は、抗菌薬治療が必要となるケースもあります。
・症状の発現後数日で嘔吐と下痢が徐々に改善していくものの、疲労感や食欲不振は1週間以上続くこともあり、十分な休息と栄養補給が重要です。
感染性胃腸炎の症状が長引く、または重度の場合は早期の受診が推奨されます。
③ 病態
感染性胃腸炎の病態は、感染した病原体が胃腸の粘膜上皮に付着し、局所の炎症反応や上皮細胞の破壊を引き起こすことにより生じます。
【ウイルス性胃腸炎の場合】
・ウイルスは小腸や大腸の上皮細胞に付着し、細胞内に侵入します。
・細胞内で増殖すると、微絨毛の破壊や細胞死を引き起こし、吸収障害が生じます。
・その結果、水分や電解質の吸収がうまくいかず、下痢を招き、局所の炎症反応により嘔吐や腹痛が誘発されます。
・ウイルスに対する免疫応答のためサイトカイン分泌が促進され、発熱や全身倦怠感につながります。
【細菌性胃腸炎の場合】
・細菌は、食品や水、接触感染などを介して胃腸に侵入し、主に小腸上皮に付着します。
・カンピロバクターやサルモネラ菌などは、細胞への侵入と毒素の産生を伴い、上皮細胞の破壊と局所的な炎症を引き起こします。
・血管透過性の亢進、粘膜の損傷、さらには炎症が生じ、腹痛や高熱、血便などの症状が発生することがあります。
・免疫反応により産生される抗体やサイトカインが、腸管内のバランスを乱すことも、症状の持続や再発の原因と考えられています。
ウイルス性も細菌性も、病原体の感染後の増殖や免疫応答により、症状がおこります。
感染者の体調や年齢、栄養状態により、重症度が変化します。特に乳幼児や高齢者では脱水症状が起こりやすく、注意が必要です。
④ 治療法
感染性胃腸炎の治療は基本的に対症療法が中心であり、特にウイルス性胃腸炎には特効薬はありません。以下、治療法の概要をご説明します。
* 対症療法
- 水分補給
脱水予防が最重要となります。経口補水液(ORS)の使用が推奨され、少量ずつ頻回に摂取することが大切です。 - 食事療法
嘔吐が落ち着いた後、消化に優しい軽食(おかゆなど)を少量ずつ摂取し、栄養補給と胃腸負担軽減を図ります。 - 解熱・鎮痛剤
発熱や痛みが強い場合は、解熱鎮痛剤が用いられます。ただし、消化管への刺激や副作用に注意が必要です。
* 薬物療法
・制酸薬
胃酸の中和を目的として、制酸薬が使用される場合があります。
・整腸剤
腸内フローラのバランスを整えるために整腸剤が処方されることがあり、回復を促進します。
* 抗菌薬の使用について
ウイルス性胃腸炎には抗菌薬は効果がなく、使用は原則として行われません。
しかし、症状が重く、または検査結果から細菌性胃腸炎が疑われる場合は、原因菌に応じた抗菌薬治療が検討されます。
* 予防策と感染拡大防止
感染性胃腸炎は高い感染力を持つため、以下のような予防策が重要です。
- 手洗いの徹底:特にトイレ使用後、食事前・後は十分な手洗いを実施する。
- 食品の適切な加熱:特に生または加熱不十分な食品、海産物の取扱いには注意が必要です。
- 環境消毒:家庭内や集団施設では、嘔吐物や便の処理後、適切な消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)での消毒が有効です。
- 感染者との接触隔離:発症者がいる場合は、周囲へのウイルス拡散防止のため、十分な分離措置を講じる。
これらの予防策の徹底が集団感染防止に極めて重要であるとされています。特にノロウイルスは、非常に低い感染量で感染を成立させるため、家庭内や施設内での衛生管理の徹底が求められます。