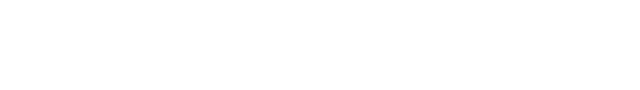僧帽弁閉鎖不全症
「最近、疲れやすくなった」「階段で息が切れる」「胸がドキドキする」──そんな症状が続いている方は、心臓の弁に異常があるかもしれません。
僧帽弁閉鎖不全症とは、左心房と左心室の間にある僧帽弁が完全に閉じず、血液が心房へ逆流してしまう病気です。これにより心臓に負担がかかり、進行すると心房が拡大し、不整脈(特に心房細動)や心不全を引き起こすことがあります。
当院では、循環器専門医として、心エコーを用いた弁膜症の正確な評価と、薬物治療・生活指導・必要時の高度医療機関への紹介まで、一人ひとりの心臓の状態にあわせた診療を行っています。
僧帽弁閉鎖不全症の症状について
僧帽弁閉鎖不全症の症状は進行とともに変化します。初期は無症状のことも多く、健診で「心雑音」を指摘されて気づかれる方もいらっしゃいます。
以下のような症状がある場合は、注意が必要です。
-
息切れ(特に運動時)
-
動悸(ドキドキする、胸が苦しい)
-
疲れやすい、倦怠感
-
夜間の咳や息苦しさ(夜間呼吸困難)
-
足のむくみ
-
横になると息苦しい(起座呼吸)
-
心房細動による脈の乱れ
進行した場合は、左心房や肺への負担が大きくなり、肺うっ血や心不全の症状が現れます。
僧帽弁閉鎖不全症の原因について
僧帽弁が閉じきらなくなる原因には、以下のようなものがあります。
変性性(加齢・組織の変化)
-
弁のひだや腱索(弁を支えるヒモのような構造)の変性
-
僧帽弁逸脱症(弁の一部が心房側にふくらむ状態)
虚血性(心筋梗塞など)
-
心筋梗塞後に弁の機能を支える筋肉が弱くなることで起こる
感染性心内膜炎
-
弁に感染(細菌など)を起こし、破壊されてしまう
リウマチ性・先天性など
-
リウマチ熱による弁の変性
-
生まれつきの弁の構造異常
また、長年の高血圧や心房細動などが原因で、左心房が拡大し、弁が閉じにくくなる場合もあります。
僧帽弁閉鎖不全症の病気の種類について
僧帽弁閉鎖不全症は、以下のように分類されます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 急性型 | 感染や心筋梗塞によって突然弁が破綻。重篤な心不全を起こすことがある |
| 慢性型 | 長期間かけて徐々に進行。心臓が代償しながら働いているため、無症状のことも |
また、重症度は心エコーでの逆流の程度や心臓の形状から評価されます。
| 重症度 | 特徴 |
|---|---|
| 軽度 | 逆流はあるが心臓への影響は少ない |
| 中等度 | 心房・心室の拡大が見られることもある |
| 高度 | 心拡大・心不全の症状あり、外科的対応の検討が必要 |
僧帽弁閉鎖不全症の治療法について
当院では、症状の有無や重症度に応じて、以下のような治療を行います。
1. 正確な検査と診断
-
心エコー検査(弁の動き、逆流の程度、心房・心室のサイズ)
-
心電図・レントゲン
-
血液検査(BNP、腎機能など)
必要時には、心臓CTやMRI、心臓カテーテル検査が可能な連携病院をご紹介いたします。
2. 内科的治療(軽症・無症状の場合)
-
利尿薬:うっ血による症状(むくみ、息切れ)を改善
-
降圧薬・β遮断薬:心臓の負担を軽減
-
抗不整脈薬や抗凝固薬:心房細動の予防や脳梗塞のリスク軽減
症状の有無にかかわらず、心臓の働きを守るために薬物治療を行います。
3. 外科的治療(重症の場合)
-
僧帽弁形成術(修復)
-
僧帽弁置換術(人工弁)
-
カテーテル治療(MitraClip)※高齢者・ハイリスクの方に
手術の適応となるかは、心機能・年齢・症状を総合的に判断し、タイミングを逃さないように連携医療機関へ紹介いたします。
僧帽弁閉鎖不全症についてのよくある質問
Q1. 健診で心雑音を指摘されました。弁膜症でしょうか?
A1. 心雑音は弁膜症のサインかもしれません。早めに心エコーで評価することをおすすめします。
Q2. 弁の異常があっても、症状がなければ治療は不要ですか?
A2. 無症状でも心臓が拡大していたり、心房細動が起きている場合は、治療が必要となることがあります。
Q3. 僧帽弁閉鎖不全症は治せますか?
A3. 薬で進行を遅らせることは可能ですが、重症の場合は外科的治療(手術)が根本的な治療になります。
Q4. スポーツや運動はできますか?
A4. 軽度で症状がなければ可能なこともありますが、状態によって制限が必要な場合もあります。医師にご相談ください。
院長より
僧帽弁閉鎖不全症は、初期には自覚症状が少ないものの、進行すると心不全や脳梗塞などにつながるおそれのある重要な病気です。
私たちゆうひ内科循環器クリニックでは、専門的な心エコーを中心に、わかりやすい説明と患者さんに合わせた治療方針をご提案しています。健診で心雑音を指摘された方、息切れや動悸を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。早期発見・早期対応が、心臓を守るカギになります。